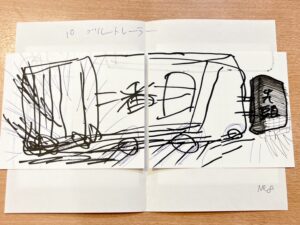サチ子さんの日常 第三章 -満点を取れないサチ子さん-
「私は長い学生時代を過ごしてきましたが、どんなに簡単な試験でも、満点を取ったことはありませんでした。99点から100点までの距離は、数光年もあるように感じられました」とサチ子さんは話す。
黒柴さんはとても怒っていました。彼が怒っているときは、冷笑が絶えず溢れます。サチ子さんは彼の冷笑を見ると、まるでハリネズミのように全身の毛が逆立ち、自分を守ろうとします。
黒柴さんの冷笑の原因は、サチ子さんがマスカット味の炭酸ジュースをコップをひっくり返してこぼしてしまったからでした。小さな書斎はマスカットの甘い香りで満ちて、サチ子さんは少し驚きました。それは、彼女が長い間探し求めていた適切な書斎の香りだったのです。しかし、この驚きは黒柴さんに伝わることはありませんでした。なぜなら、その甘いマスカットの液体は黒柴さんが昨夜、徹夜で書いた原稿を湿らせてしまったのです。
湿った原稿を持ちながら、黒柴さんは悲壮な表情を浮かべていました。サチ子さんが謝罪しても、彼はなかなか立ち直ることができませんでした。サチ子さんも許しを請うのを諦め、広がるシミを眺めていると、昔の思い出の中に入り込んでいきました。
小学校の頃、サチ子さんの従姉妹が彼女の机の上で、ミルクの瓶を倒してしまったことを憶えています。そのミルクはサチ子さんの教科書や宿題を濡らしました。しかし、サチ子さんの心には一つの怒りもなく、むしろ喜びに満ちていました。
「私がこぼしたわけじゃない、なんて幸運で素晴らしいことなのだろう」
サチ子さんは心から幸せを感じました。そうです、このようなことはサチ子さんの人生でよくあることでした。サチ子さんの脚や腕には、よく打撲のあざがありました。彼女は歩いていると、頻繁に体をどこかにぶつけてしまいます。サチ子さんは新しいあざを見るたびに、しばらく理解に苦しむことになります。
「これは、いつぶつけたんだろう」
後に仕事を始めると、サチ子さんは提出する書類を何度も注意深く確認する癖ができました。しかし、長腕上司に提出すると、いつも間違いを指摘され、一度もうまくいったことはありませんでした。長腕上司の眼球には、顕微鏡が付いていて虱を捕まえるように、サチ子さんの文書にたくさんの注釈をつけました。
2000年の初めの頃、テレビドラマでは、ドジっ子タイプのヒロインが流行りました。サチ子さんのお友達はお菓子を慣れた手つきで口に入れると、「平らな道を歩いて転ぶ人がいるか!」と大声で文句を言います。サチ子さんもお菓子を口に入れ、にやりと笑いました。友達は存じ上げていないが、そのような人は実際に存在し、むしろ非現実的なのは、平らな道で転んだ時、あなたに手を差し伸べる人がいないということだけです。
ドラマのような展開も待ち合わせていないサチ子さんにとって、自分が間違えなかったということは、とても幸福なことなのです。
サチ子さんは前の仕事を辞める時、上司に言いました。
「気をつけなさいと仰いますけど、私は生まれてから幾度となく細心の注意を払うことを心掛けて来ましたし、今度こそはと何度も自分を変えようとしました。しかし、これは私の習性なのです。あなたが今さら変わるようにと言っても、数か月で変わることはできません」
眠れない人がなぜ眠れないのか、それを理解できない人がいます。彼らは、湯船に浸かり、ホットミルクを飲んで、ベッドで横になって思考を巡らせない限り、すぐに眠れるとアドバイスをします。しかし、不眠症の人にとっては、そのホットミルクに睡眠薬を入れない限りは、不可能なことなのです。
だから、彼女は自分の心の中には黒い穴があるように感じられ、数学の問題を解く方程式を知らない内にに忘れてしまったり、グラスが知らない内に割れたり、注いでいたグラスから水が知らない内に溢れたり、足が知らない内に青ざめたりします。そう、しっかりと道を歩いていても、知らない内につまずいてしまうのです。
サチ子さんは、この黒い穴を持たない人たちに、この穴がどれほど恐ろしいものかを説明することができません。「気をつけなさい」「慎重に行動しなさい」という言葉を吸い込むほど、この黒い穴は恐ろしいのです。徐々に、サチ子さんはこの黒い穴と共存する方法を学び、その負の影響に耐える方法を学びました。もちろん、克服しようとも試みましたが、ガラスの割れる音が鳴る度に、その試みは失敗に終わりました。
この共存には大きな利点があります。サチ子さんは他人が何かミスをして、自分が被害を被ったとしても怒りの感情は少しも湧きません。それは、表面的に大丈夫と言って取り繕い心の中では、憎しみを堪えているものではなく、全身全霊で相手を理解している寛容さです。
この黒い穴の名前は、「完璧なくすり穴」と呼ばれています。それはサチ子さんが完璧な人になること、完璧なことを成し遂げることができないということを運命づけています。
ある時、サチ子さんが目玉焼きを焼いていると、うっかりフライ返しで黄身を傷つけてしまいました。黄金色の黄身は透明な切れ目から広がり、隣の白身と分け隔てなくなってしまいました。焼き終えた後、サチ子さんは少し醤油をつけてその卵を食べましたが、とても美味しい感じました。